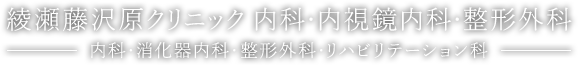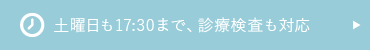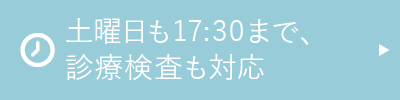炎症性腸疾患について
炎症性腸疾患とは、大腸に炎症を起こす疾患の総称です。ウイルスや細菌によって発症する急性のものや、潰瘍性大腸炎やクローン病のように、原因が解明されていない難病まで多岐に渡ります。発症して悪化すると、粘膜にただれや潰瘍、びらんができます。
考えられる原因が多岐に渡るため、心当たりのある方は、専門医の治療を受けることをお勧めします。
潰瘍性大腸炎
潰瘍性大腸炎とは
大腸の粘膜に炎症が起こり、びらんや潰瘍ができる慢性疾患です。主な症状としては、下痢や腹痛、粘血便、体重減少、発熱などが挙げられ、症状が目立つ「活動期」と症状が治まる「寛解期」を繰り返す特徴を持っています。20~30代の発症者が多い傾向にありますが、40~60代の中高年の方が発症するケースも少なくありません。以前は日本人の患者数が少なかった疾患でしたが、近年では増加傾向にあります。
原因が解明されておらず、根治させる治療法も存在していないため、厚生労働省からは難病として指定されています。しかし、炎症を抑える治療は確立されているため、適切な治療を受け続けていけば、発症前とほとんど同じ生活を送ることができます。
潰瘍性大腸炎は指定難病ですので、一定の基準を満たせば医療費助成制度の対象にもなります。
潰瘍性大腸炎の症状
 下痢や腹痛、粘血便をはじめ、発熱や貧血、体重減少などが起こります。直腸に炎症が起こると、「頻繁に便意を感じる」「便が体内に残っているような感覚がある」といった症状も伴います。皮疹や関節炎などといった、腸管以外の部位に症状が現れることがあります。
下痢や腹痛、粘血便をはじめ、発熱や貧血、体重減少などが起こります。直腸に炎症が起こると、「頻繁に便意を感じる」「便が体内に残っているような感覚がある」といった症状も伴います。皮疹や関節炎などといった、腸管以外の部位に症状が現れることがあります。
治療を受けてある程度の期間を過ぎると症状がぶり返してしまう「再燃寛解型」や、症状が長引く「慢性持続型」などに分類できます。残念なことに、現代の医療技術では根治できない疾患ですので、寛解期になっても治療を受け続けなくてはなりません。
ある程度治療を続けて症状が消えた後に、自己判断で治療を止めたことで再発するという悪循環を繰り返すと、ますます症状も悪化しやすくなります。突然の重症化や発がんのリスクも高くなりますので、症状が落ち着いた後でも治療をコツコツ続けていきましょう。
潰瘍性大腸炎の原因
大腸粘膜に対して免疫が過剰に反応することで発症すると考えられています。しかし、遺伝や食習慣、ストレス、腸内細菌叢などの要因が複数積み重なることで発症するとも考えられており、ハッキリとした原因は不明のままでいます。
潰瘍性大腸炎の検査と診断
 びまん性・連続的な炎症を見つけ出すのに有効な、大腸カメラ検査を行ってから診断をくだします。潰瘍性大腸炎になると、大腸粘膜の全周に炎症が直腸から連続的に起こります。この炎症箇所に応じて、直腸炎型・左側大腸炎型・全大腸炎型と分類されます。大腸カメラ検査では検査中に組織を採取し、病理組織学的検査を行うことが可能です。確定診断は病理検査を行ってから行います。血液検査では、貧血をはじめ炎症や栄養不良の重症度をチェックします。
びまん性・連続的な炎症を見つけ出すのに有効な、大腸カメラ検査を行ってから診断をくだします。潰瘍性大腸炎になると、大腸粘膜の全周に炎症が直腸から連続的に起こります。この炎症箇所に応じて、直腸炎型・左側大腸炎型・全大腸炎型と分類されます。大腸カメラ検査では検査中に組織を採取し、病理組織学的検査を行うことが可能です。確定診断は病理検査を行ってから行います。血液検査では、貧血をはじめ炎症や栄養不良の重症度をチェックします。
潰瘍性大腸炎を放置しておくと大腸がんのリスクが上昇するため、症状が落ち着いた後でも、定期的に大腸カメラ検査は受けるようにしましょう。これにより、大腸がんやポリープがより早期に発見されやすくなります。粘膜の状態もリアルタイムでチェックできますので、患者様に適した治療にも繋がります。
潰瘍性大腸炎の治療
 症状の程度に応じた治療を続けていくことで、症状のない時期を長く続けられるようにします。治療ではサラゾピリンやペンタサ、アサコール、リアルダといった5-ASA系薬剤を主に用いますが、容態によっては免疫抑制剤(イムラン)やステロイド薬、注腸製剤、坐剤を用いることもあります。先述した治療法を続けても改善されない場合は、炎症を引き起こす白血球を血液から取り除く「白血球除去療法(LCAP:血液透析と似た、血液浄化療法)を検討する可能性もあります。重度の炎症がみられる方には、ステロイド薬を静脈内に投与したり、生物学的製剤や免疫調節薬などを処方したりする治療法を検討します。重い炎症が広範囲にまで及んでいる場合は、食事を抜いて腸管を休ませたり、中心静脈栄養を投与したりします。
症状の程度に応じた治療を続けていくことで、症状のない時期を長く続けられるようにします。治療ではサラゾピリンやペンタサ、アサコール、リアルダといった5-ASA系薬剤を主に用いますが、容態によっては免疫抑制剤(イムラン)やステロイド薬、注腸製剤、坐剤を用いることもあります。先述した治療法を続けても改善されない場合は、炎症を引き起こす白血球を血液から取り除く「白血球除去療法(LCAP:血液透析と似た、血液浄化療法)を検討する可能性もあります。重度の炎症がみられる方には、ステロイド薬を静脈内に投与したり、生物学的製剤や免疫調節薬などを処方したりする治療法を検討します。重い炎症が広範囲にまで及んでいる場合は、食事を抜いて腸管を休ませたり、中心静脈栄養を投与したりします。
これらの治療を継続すれば高い効果が得られやすくなりますが、それでも改善が難しい場合や中毒性巨大結腸症によって大腸が破れ、腹膜炎や敗血症を発症するリスクが高い場合は、大腸を摘出する手術が選択されます。
クローン病
クローン病とは
消化管全域に炎症を起こし、小腸や大腸を中心に潰瘍やびらんができる慢性疾患です。発症年齢は20代が一番多いですが、どの年代の方でも発症する可能性はあります。原因が不明なため根治する方法も確立されておらず、厚生労働省からは難病として指定されています。クローン病を発症している方は、医療費助成制度を受けられる可能性があります。潰瘍性大腸炎と極めて似ている疾患ですが、潰瘍性大腸炎は主に、大腸粘膜に炎症が起こる疾患です。一方、クローン病は口内から肛門まで、消化管全域に炎症が起こり得る疾患です。クローン病による炎症の場合、粘膜の表層だけでなく深い筋層にまで及ぶ(全層性の炎症)ケースがあります。
クローン病の症状
 下痢や腹痛、発熱、血便、体重減少、全身の倦怠感、貧血などの症状がみられます。炎症が小腸までに至っている場合は、血便や下痢が起こりません。しかし、腸管の狭窄(きょうさく)によって、便秘や腸閉塞に陥る恐れがあります。
下痢や腹痛、発熱、血便、体重減少、全身の倦怠感、貧血などの症状がみられます。炎症が小腸までに至っている場合は、血便や下痢が起こりません。しかし、腸管の狭窄(きょうさく)によって、便秘や腸閉塞に陥る恐れがあります。
炎症が直腸や肛門にまで及んでいる場合は、肛門周囲潰瘍や痔ろうなどの肛門疾患を合併しやすくなります。実際に、肛門周囲潰瘍や痔ろうの発症をきっかけに、クローン病に気付く方もいらっしゃいます。関節炎や皮疹などが生じるケースもあります。
クローン病の原因
残念ながら、ハッキリした原因は分かっていません。しかし、遺伝や消化管での過剰な免疫反応が発症と大きく関わっているのではないかと考えられています。食習慣の欧米化に伴って患者数が増えているため、動物性脂肪の摂りすぎや食物繊維の摂取不足、腸内細菌叢の乱れなども関与しているのではないかと言われています。
クローン病の検査と診断
 クローン病は、全消化管に炎症が起こり得る疾患です。しかし、小腸のみに病変がみられる「小腸型」、大腸のみにみられる「大腸型」そして、大腸と小腸の両方にみられる「小腸大腸型」というようにも分類できます。一番多いのは、回腸の末端と盲腸に炎症が起こるタイプです。クローン病による炎症は連続的に起こるわけではありません。正常粘膜内に病変が点在することもあります。細長い潰瘍ができたり、敷石を敷いたような変化が起こったりするなど、特徴的な病変が起こるケースも多いです。
クローン病は、全消化管に炎症が起こり得る疾患です。しかし、小腸のみに病変がみられる「小腸型」、大腸のみにみられる「大腸型」そして、大腸と小腸の両方にみられる「小腸大腸型」というようにも分類できます。一番多いのは、回腸の末端と盲腸に炎症が起こるタイプです。クローン病による炎症は連続的に起こるわけではありません。正常粘膜内に病変が点在することもあります。細長い潰瘍ができたり、敷石を敷いたような変化が起こったりするなど、特徴的な病変が起こるケースも多いです。
確定診断するには、大腸カメラ検査による観察や、組織を採取して行う病理検査が必要になります。特徴的な病変がみられないケースでも、採取した組織の中に、クローン病特有の非乾酪性の類上皮細胞肉芽腫がみられると確定診断が可能です。小腸の粘膜は大腸カメラ検査で確認できないため、小腸造影検査でチェックします。食道や胃・十二指腸の粘膜は胃カメラ検査で観察できます。必要に応じて血液検査も行い、炎症の度合いや貧血が隠れていないか、栄養状態をチェックすることがあります。
クローン病の治療
 潰瘍性大腸炎と同じように、ペンサタなどの5-ASA製剤を中心とした薬物療法を行います。容態に合わせて、免疫抑制薬や副腎皮質ステロイド薬、エレンタール(液体食)などの成分栄養剤などを用います。
潰瘍性大腸炎と同じように、ペンサタなどの5-ASA製剤を中心とした薬物療法を行います。容態に合わせて、免疫抑制薬や副腎皮質ステロイド薬、エレンタール(液体食)などの成分栄養剤などを用います。
クローン病は潰瘍性大腸炎と違い、炎症が消化管の広範囲にまで及ぶ疾患です。炎症により栄養状態が悪化しやすいため、先述したように成分栄養剤を使うことがあります。成分栄養剤は、アミノ酸などの成分が主体でできており、炎症を引き起こす脂肪などの食事抗原は入っていません。栄養状態の改善を目的に使うのはもちろん、腸管の安静にも有効とされています。ただし容態が良くない場合は、静脈から栄養を補給します。
近年では、レミケードやヒュミラ、ステラーラなどの生物学的製剤(抗TNF-α抗体製剤)を用いた薬物療法が行われるようになり、従来の治療よりも効果が実感できやすくなりました。ただし、炎症によって小腸が狭くなったり瘻孔(ろうこう)ができたりすることで、腸閉塞や腹腔内膿瘍を引き起こした場合は、手術を余儀なくされます。